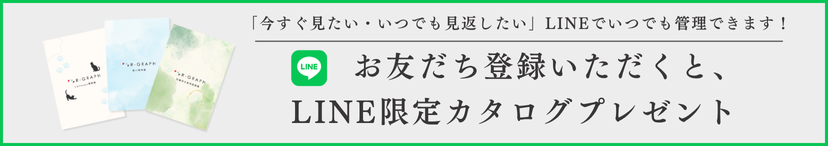BLOG ブログ
制振装置とは?耐震・免震との違いから、選び方まで専門家が徹底解説
マイホームの新築や購入を考えるとき、近年の地震の多発に不安を感じる方は少なくありません。
「家族の安全を守るために、地震に強い家を建てたい」と願うのは当然のことです。
ハウスメーカーや工務店との打ち合わせで「制振装置」という選択肢を提示され、その必要性について真剣に考え始めた方もいらっしゃるでしょう。
しかし、「耐震や免震と何が違うの?」「高額な費用をかけてまで導入する価値はあるの?」といった疑問や不安も同時に生まれてくるはずです。
この記事では、そんな家づくりを真剣に考えるあなたのために、制振装置の基礎知識から専門家ならではの視点まで、わかりやすく徹底解説します。
最後までお読みいただくことで、制振装置に関するあらゆる疑問が解消され、ご自身の家づくりにおいて後悔のない最適な選択ができるようになります。
大切な家族と資産を守るための確かな知識を、ぜひここで手に入れてください。
目次
そもそも「制振装置」とは?地震から家を守る仕組みをわかりやすく解説

制振装置とは、地震の揺れを吸収し、建物の変形や損傷を抑えるための装置です。
例えるなら、自動車のサスペンションについている「ショックアブソーバー」のような役割を果たします。
路面の凹凸による衝撃をショックアブソーバーが吸収して快適な乗り心地を保つように、制振装置は地震のエネルギーを吸収して、建物の揺れを穏やかにするのです。
この「揺れを吸収する」という点が、建物を硬くして揺れに耐える「耐震」とは大きく異なるポイントです。
制振の基本原理:「揺れ」のエネルギーを「熱」エネルギーに変換して吸収
制振装置が揺れを抑える基本的な仕組みは、地震によって生じる「運動エネルギー」を「熱エネルギー」に変換して放出することにあります。
例えば、手を素早くこすり合わせると温かくなりますが、これも摩擦による運動エネルギーが熱エネルギーに変わる現象です。
制振装置も同様に、内部の素材(オイル、ゴム、鋼材など)が動いたり変形したりする際の抵抗を利用して、揺れのエネルギーを吸収し、熱に変えて逃がすことで建物の揺れを小さくします。
この仕組みにより、構造体へのダメージを直接的に軽減することができるのです。
なぜ今「耐震+制振」が注目されるのか?建物の寿命を守る重要性
日本の建築基準法では、大規模な地震で建物が倒壊しないための「耐震性能」が義務付けられています。
しかし、これはあくまで「命を守る」ための最低限の基準であり、一度大きな地震に耐えたとしても、建物が無傷でいられるわけではありません。
繰り返し発生する余震や、震度5弱程度の中規模な地震でも、建物の構造には目に見えないダメージが少しずつ蓄積されていきます。
「耐震」に「制振」をプラスすることで、これらのダメージの蓄積を大幅に抑制し、大切な住まいの資産価値と寿命を守ることにつながるため、近年特に注目されているのです。
【比較で一目瞭然】「耐震」「免震」「制振」それぞれの違いとは?

地震対策と聞くと、「耐震」「免震」「制振」という3つの言葉をよく耳にしますが、その違いを正確に理解されている方は少ないかもしれません。
それぞれの対策には異なる目的と特徴があり、ご自身の予算やライフプランに合わせて最適なものを選ぶことが重要です。
ここでは、それぞれの違いがひと目でわかるように比較してみます。
【耐震】
- 目的:建物の強度を高め、揺れに「耐える」
- 仕組み:柱や梁、壁を強化し、建物自体を頑丈にする
- メリット:コストが比較的安い・多くの住宅で採用されている標準的な工法
- デメリット:建物内部は大きく揺れる・家具の転倒リスクが高い・繰り返しの揺れでダメージが蓄積する
【免震】
- 目的:揺れを建物に「伝えない」
- 仕組み:建物と基礎の間に積層ゴムなどの装置を設置し、地盤と切り離す
- メリット:揺れを大幅に低減でき、建物・家具の被害が最も少ない・地震後も住み続けられる可能性が高い
- デメリット:コストが非常に高い・設置できる地盤や土地の形状に制約がある・定期的なメンテナンスが必要・台風などの強風による小さな揺れには効果がない
【制振】
- 目的:揺れのエネルギーを「吸収する」
- 仕組み:建物内部にダンパーなどの装置を設置し、揺れのエネルギーを熱などに変換
- メリット:繰り返しの地震に強い・耐震に比べ建物の損傷を抑えられる・免震よりコストが安い・台風などの強風にも効果がある
- デメリット:耐震構造が前提となる・免震ほどの揺れ低減効果はない・製品によってはメンテナンスが必要
「耐震」「免震」「制振」の具体的な震災対策はこちらです。
耐震:建物の強度で地震に「耐える」基本的な対策
耐震構造は、現在の日本の住宅において最も基本的で、法律で定められている地震対策です。
その主な目的は、太い柱や頑丈な壁で建物自体を固くし、震度6強から7程度の大地震でも即座に倒壊・崩壊しないようにすることです。
あくまで人命を守ることが最優先の考え方であり、コストを比較的安く抑えられるメリットがあります。
しかし、建物自体は地面と一緒に大きく揺れるため、室内の家具が転倒したり、壁紙が破れたりするリスクは避けられません。
免震:揺れを建物に「伝えない」最も効果が高い対策
免震構造は、地震対策の中で最も揺れを抑える効果が高い方法です。
建物と基礎(地面)の間に積層ゴムやダンパーといった特殊な装置を挟み込むことで、地震の揺れが建物に直接伝わるのを防ぎます。
建物自体はほとんど揺れないため、建物はもちろん、家具や家電への被害も最小限に抑えることが可能です。
ただし、その効果は絶大ですが、導入コストが数百万円単位と非常に高額になることや、設置できる土地の条件が限られるといったデメリットもあります。
制振:揺れのエネルギーを「吸収」し損傷を抑える対策
制振構造は、耐震と免震の長所を併せ持つ、いわば「良いとこ取り」のバランスの取れた対策といえます。
耐震構造を基本としながら、建物内に設置した制振装置が地震のエネルギーを吸収し、揺れを穏やかにします。
これにより、建物の構造体へのダメージを軽減し、資産価値を長期的に守ることができます。
特に、一度きりの大地震だけでなく、繰り返し起こる余震にも効果を発揮するのが大きな強みです。
制振装置を導入する現実的なメリット|家族と資産を守る効果とは

制振装置を導入するメリットは、単に「揺れが小さくなる」だけではありません。
その効果は、ご家族の安全、大切な住まいの資産価値、そして日々の暮らしの安心感にまで及びます。
ここでは、制振装置がもたらす具体的で現実的なメリットを4つのポイントに分けて解説します。
メリット1:繰り返す地震による「見えないダメージ」の蓄積を防ぐ
一度大きな地震を経験した建物は、たとえ見た目に問題がなくても、構造内部に微細な損傷を負っている可能性があります。
その後も続く余震や中小規模の地震によって、その「見えないダメージ」は着実に蓄積され、建物の耐震性能を徐々に低下させてしまいます。
制振装置は、こうした小さな揺れの段階からエネルギーを吸収してくれるため、ダメージの蓄積を効果的に防ぎ、建物の寿命を延ばすことに貢献します。
メリット2:建物の変形を最大50%以上抑制し、内外装の損傷を軽減
地震の際、建物は大きくしなるように変形し、その変形量が大きいほど壁や柱へのダメージも深刻になります。
制振装置を設置することで、この建物の変形(層間変位)を最大で50%以上も抑制することが可能です。
揺れが小さくなることで、壁紙のひび割れや亀裂、外壁の剥がれといった内外装の損傷を大幅に減らすことができます。
これは、将来的に発生しうる高額な修繕費用を未然に防ぐことにも直結します。
メリット3:家具の転倒リスクを減らし、室内の安全性を高める
地震による怪我の原因の多くは、倒れたり、落ちてきたりした家具によるものだと言われています。
制振装置によって建物自体の揺れが穏やかになれば、当然、室内の家具が転倒するリスクも低減します。
背の高い本棚や食器棚が倒れてくる危険性を減らすことは、ご家族の命を守る上で非常に重要なポイントです。
日々の暮らしの中で、地震への不安を和らげ、より高い安全性を確保することにつながります。
メリット4:台風などの強風による揺れにも効果を発揮
制振装置の活躍の場は、地震だけに限られません。
特に、住宅の2階や3階では、台風や春一番などの強い風によって建物が揺れ、不快感や不安を感じることがあります。
制振装置は、このような風による建物のゆっくりとした揺れに対しても効果を発揮します。
地震という非日常の災害だけでなく、日常的に発生しうる揺れを抑え、住まいの快適性を向上させるメリットもあるのです。
導入前に知っておきたい制振装置のデメリットと注意点

制振装置は多くのメリットをもたらしますが、導入を決定する前に知っておくべきデメリットや注意点も存在します。
良い面と悪い面の両方を正しく理解し、ご自身の家づくりに本当に必要かどうかを冷静に判断することが後悔しないための鍵となります。
ここでは、事前に把握しておくべき3つのポイントを解説します。
デメリット1:初期費用(設置コスト)がかかる
制振装置の導入における最大のデメリットは、やはり初期費用が発生することです。
多くのハウスメーカーや工務店ではオプション扱いとなり、その費用は製品の種類や設置本数、建物の規模によっても異なりますが、一般的には50万円から150万円程度が相場とされています。
決して安い金額ではないため、家づくり全体の予算とのバランスを考える必要があります。
ただし、この費用を住宅ローンに組み込むことで、月々の負担を抑えながら導入することも可能です。
デメリット2:製品によっては定期的なメンテナンスが必要な場合も
制振装置の多くはメンテナンスフリーを謳っていますが、製品の種類によっては定期的な点検やメンテナンスが必要になる場合があります。
例えば、オイルダンパーの場合、長期間の使用でオイルが漏れる可能性はゼロではありません。
製品を選ぶ際には、その製品がメンテナンスフリーであるか、もしメンテナンスが必要な場合はどのような内容で、どのくらいの費用がかかるのかを事前にしっかりと確認しておくことが重要です。
デメリット3:耐震性能が低い家では効果を最大限に発揮できない
非常に重要な注意点として、制振装置はそれ単体で機能するものではないということが挙げられます。
あくまで建物自体の強度、つまり「耐震性能」がしっかりと確保されていることが大前提となります。
建物が揺れに耐える力(耐震)があって初めて、その揺れを吸収する力(制振)が最大限に活かされるのです。
最低でも建築基準法で定められた耐震等級1を満たし、理想を言えば防災拠点と同レベルの「耐震等級3」を確保した上で、制振装置の導入を検討することをおすすめします。
【種類別】我が家に最適な制振装置の選び方|特徴と費用相場を比較

制振装置にはいくつかの種類があり、それぞれに異なる特徴や費用感があります。
「どれを選べば良いのかわからない」という方のために、ここでは戸建て住宅で主に採用される代表的な3つのタイプについて、その特徴を比較しながら解説します。
ご自身の予算や、どのような性能を重視したいかに合わせて、最適な装置を見つけるための参考にしてください。
オイルダンパー:小さな揺れから効果を発揮する高性能タイプ
オイルダンパーは、シリンダーに封入されたオイルがピストンの動きに抵抗することで、地震のエネルギーを吸収します。
この仕組みは、高級車の乗り心地を良くするショックアブソーバーにも使われている技術です。
最大の特徴は、震度1程度の小さな揺れから、震度7クラスの大きな揺れまで、幅広い範囲で安定した性能を発揮することです。
性能が高い分、他のタイプに比べてコストは高くなる傾向がありますが、世界的な超高層ビルでも採用実績のある信頼性の高い方式といえます。
粘弾性ダンパー(ゴムダンパー):コストと性能のバランス型
粘弾性ダンパーは、高層ビルの基礎部分などにも使われる特殊なゴムを木造住宅用に改良したものです。
地震の揺れによってゴムが伸び縮みする際に、揺れのエネルギーを熱に変えて吸収します。
比較的リーズナブルな価格で導入でき、コストと性能のバランスが良いのが魅力です。
製品によってゴムの素材や性能に差があるため、どのような揺れに効果を発揮するのか、耐久性はどのくらいかなどをしっかりと比較検討することが重要です。
鋼材ダンパー:大きな揺れに強いシンプル構造タイプ
鋼材ダンパーは、特殊な鋼(鉄)の板が地震の力で「降伏」する(塑性変形する)際のエネルギーを利用して揺れを吸収します。
構造が非常にシンプルで、メンテナンスが不要な製品が多いのが特徴です。
コストも比較的安く抑えられますが、効果を発揮するためにはある程度大きな揺れ(建物の変形)が必要となります。
そのため、中小規模の地震や風揺れに対しては、効果を感じにくい場合があります。
【実績】アールグラフが制振装置「evoltz」を標準採用する理由

私たちアールグラフは、お客様に心から安心して永く暮らしていただける住まいを提供するため、数ある地震対策の中から最適なものを追求し続けてきました。
その結果、私たちは現在、最高等級である「耐震等級3」の取得を標準とするとともに、高性能オイルダンパー「evoltz(エヴォルツ)」を全棟に標準採用しています。
ここでは、私たちがなぜこの選択に至ったのか、その背景にある家づくりへの想いと、お客様への約束をお伝えします。
「耐震等級3」は当たり前。その先の“真の安心”を追求する私たちの家づくり
法律で定められた耐震基準をクリアすることは、プロとして当然の責務です。
私たちは、消防署や警察署といった防災拠点と同レベルの「耐震等級3」をすべての住まいで実現しています。
しかし、私たちはそれで満足することはありませんでした。
基準をクリアするだけでなく、大地震の後も大きな修繕をすることなく住み続けられ、日々の暮らしの中で感じる地震への不安を少しでも和らげることこそが“真の安心”だと考えています。
その“プラスアルファの安心”を実現するために、私たちは制振装置の導入を標準仕様とすることを決断しました。
なぜ「evoltz」なのか?決め手となった世界最高レベルの性能と実績
数多くの制振装置の中から、私たちが「evoltz」を選んだのには明確な理由があります。
その決め手は、世界トップクラスの技術力に裏打ちされた圧倒的な性能と信頼性です。
F1のレーシングカーにも採用されるドイツのビルシュタイン社が開発したこのオイルダンパーは、震度1というごくわずかな揺れにも反応し、建物の変形を最大で80%も低減する性能を持っています。
また、200万回以上もの作動試験をクリアする驚異的な耐久性を誇り、メンテナンスフリーで長期にわたる安心をお約束できる点も、お客様の大切な資産をお預かりする私たちにとって大きな魅力でした。
施主様の声:制振装置のある暮らしで得られた「日々の安心感」
理論上の性能だけでなく、実際に住まうお客様が何を感じるかが最も重要です。
アールグラフで家を建てられ、「evoltz」のある暮らしをされている施主様からは、嬉しいお声をたくさんいただいています。
「夜中に地震速報のアラームが鳴っても、以前のアパートに住んでいた頃より落ち着いていられるようになった」「台風の時に2階にいても、家の揺れをほとんど感じず、静かに過ごせた」といった声は、制振装置がもたらすものが、単なる物理的な効果だけでなく、日々の暮らしにおける「心の平穏」であることを教えてくれます。
制振装置に関するよくある質問(Q&A)

ここでは、制振装置についてお客様からよくいただくご質問とその回答をまとめました。
導入を検討する上での最後の疑問や不安を解消するためにお役立てください。
Q1. 後からリフォームで設置することはできますか?
はい、既存の住宅にリフォームで制振装置を後付けすることは可能です。
壁の内側や床下などに設置するリフォーム向けの製品も数多く開発されています。
ただし、新築時に設置する場合と比較して、壁を一度剥がすなどの工事が必要になるため、費用が割高になる傾向があります。
また、建物の構造によっては設置できる製品や場所が限られる場合もあるため、マイホームを新築されるタイミングで検討するのが最も効率的かつ効果的といえるでしょう。
Q2. 木造住宅でも効果はありますか?
はい、むしろ木造住宅にこそ制振装置は非常に効果的です。
木造住宅は、鉄骨造やRC(鉄筋コンクリート)造に比べて、構造的にしなやかで揺れやすいという特性があります。
その揺れを制振装置が効率よく吸収してくれるため、相性は抜群といえます。
現在、市場に出ている多くの制振装置は、日本の住宅で最も一般的な木造軸組工法(在来工法)に合わせて開発されていますので、安心して導入をご検討いただけます。
まとめ:納得のいく選択で、地震に負けない“本当に安心できる住まい”を

この記事では、制振装置の基本的な仕組みから、耐震・免震との違い、種類別の選び方までを詳しく解説してきました。
- 耐震:【基本】建物を頑丈にし、揺れに耐える。
- 免震:【理想】揺れを伝えず、被害を最小限に。
- 制振:【賢い選択】揺れを吸収し、建物のダメージを軽減。
地震大国である日本において、建物の強度を高める「耐震」は家づくりの大前提です。
その上で、より高いレベルの安全と安心を追求するならば、「免震」は理想的な選択肢ですが、現実的にはコストの壁が大きく立ちはだかります。
そこで、耐震性能を確実に確保した上で「制振装置」をプラスすることは、手の届く価格で住まいの安全性を格段に高め、繰り返す地震から大切な家族と資産を守るための、非常に賢明で現実的な選択肢といえるでしょう。
最終的な判断は、ご自身の価値観や予算と照らし合わせながら行うことが大切です。
この記事で得た知識をもとに、ぜひ建築を依頼する工務店やハウスメーカーの担当者と深く話し合い、あなたとご家族にとって「本当に安心できる住まい」を実現してください。