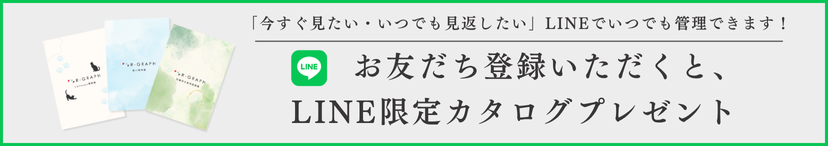BLOG ブログ
住宅の耐震等級とは?1・2・3の違いをプロが徹底解説!後悔しない家選びの決定版
「大きな地震が来ても、この家なら家族を守れるだろうか」
「家づくりで失敗したくないけれど、何から考えればいいか分からない」
これから住宅の購入や建築を考えている方にとって、家族の安全は最も大切なことの一つですよね。
特に、地震が多い日本では「耐震性」が重要なキーワードになります。
しかし、「耐震等級」という言葉は聞いたことがあっても、等級1、2、3の具体的な違いや、それがコストや住宅ローン、そして何より実際の安全性にどう影響するのか、正確に理解するのは難しいものです。
この記事では、住宅の耐震性に関するあらゆる疑問にお答えします。
耐震等級の基本的な知識から、それぞれの等級が持つ意味、メリット・デメリット、さらには費用面への影響まで、専門的な内容を分かりやすく徹底的に解説します。
この記事を最後まで読めば、あなたとご家族にとって最適な住宅性能が何なのかが明確になり、自信を持って後悔のない家選びができるようになるでしょう。
目次
そもそも耐震等級とは?「耐震基準」との違いも解説

家づくりを考える上で、まず押さえておきたいのが「耐震等級」と「耐震基準」という2つの言葉です。
これらは似ているようで、実は全く異なる意味を持っています。
耐震等級とは、2000年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づく、建物の地震に対する強さを示す指標です。
これは、住宅の性能を分かりやすく示すための「ものさし」のようなもので、取得は任意となっています。
一方で、耐震基準は「建築基準法」で定められた、建物が満たさなければならない最低限の耐震性能のことです。
つまり、日本国内で家を建てる以上、すべての住宅は必ずこの耐震基準をクリアしている必要があります。
両者の違いを簡単にまとめると、以下のようになります。
- 品確法
- 目的:住宅性能の分かりやすい表示
- 位置づけ:任意(より高い性能を目指す指標)
- 段階:性能項目ごとに複数の等級がある(例:耐震等級1~3、断熱等級1~7など)
- 建築基準法
- 目的:最低限の安全性の確保
- 位置づけ:義務(すべての建物が満たすべき最低ライン)
- 段階:一つの基準のみ
また、地震対策には「耐震」の他に「制震」「免震」といった考え方もあります。
耐震は建物の構造自体を頑丈にして揺れに耐える技術ですが、制震はダンパーなどで揺れを吸収し、免震は特殊な装置で地面の揺れを建物に伝わりにくくする技術です。
耐震等級は、この「耐震」性能に焦点を当てた指標となります。
耐震等級1・2・3の違いは?どのくらいの地震に耐えられる?
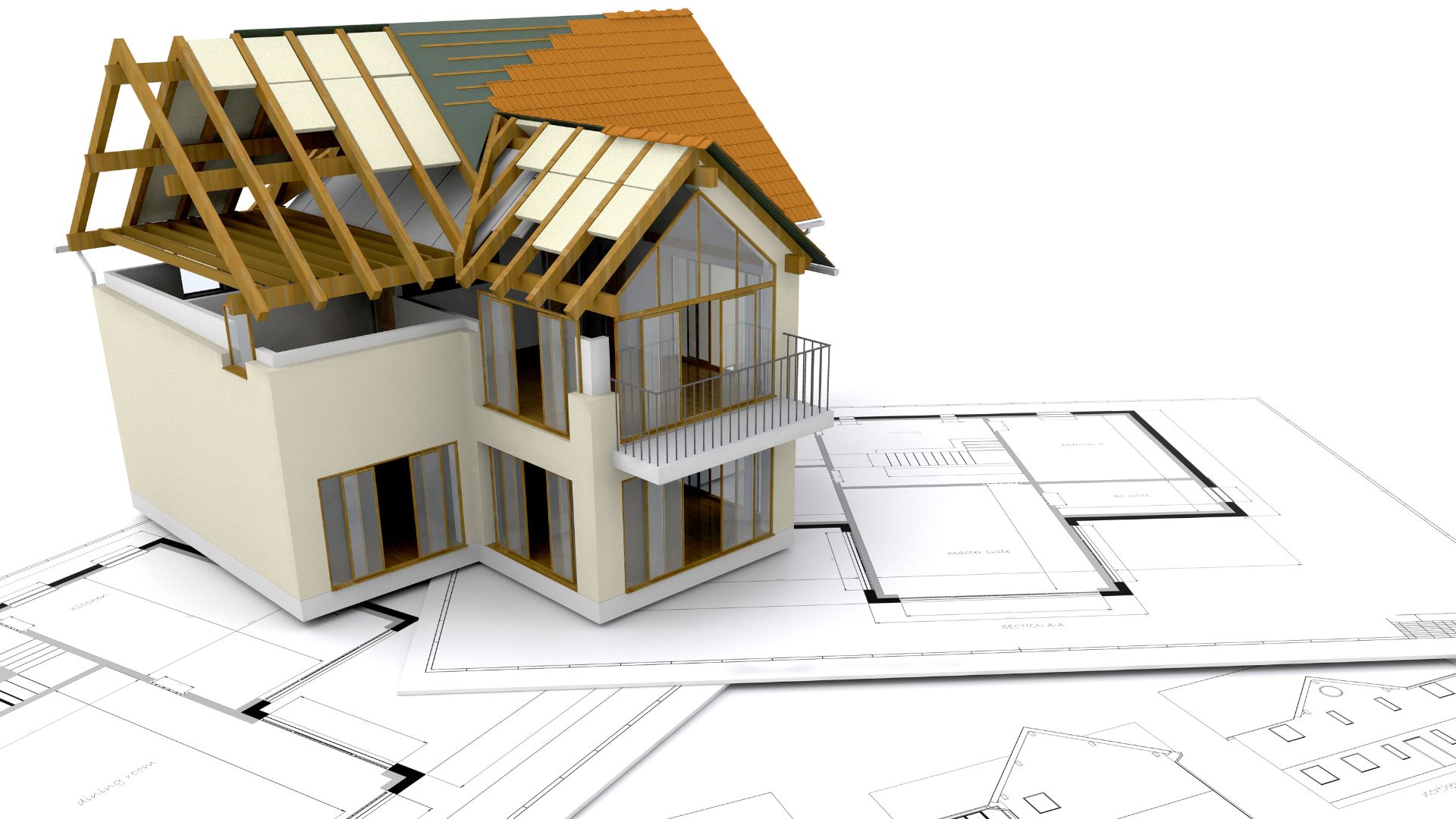
耐震等級は1から3までの3段階に分かれており、数字が大きいほど高い耐震性能を持つことを示します。
それぞれの等級がどのくらいの地震に耐えられ、建物にどのような影響があるのかを知ることが、家選びの重要な第一歩です。
ここでは、「等級ごとの強度」「想定される地震」「建物への影響」という3つのポイントで、各等級の違いを比較してみましょう。
- 耐震等級1
- 震度6強~7
- 強度の目安 (建築基準法の何倍か):1.0倍
- 地震後の建物への影響と生活:倒壊・崩壊はしないが、大規模な修繕や建て替えが必要になる可能性。住み続けるのは困難な場合も。
- 耐震等級2
- 震度6強~7
- 強度の目安 (建築基準法の何倍か):1.25倍
- 地震後の建物への影響と生活:倒壊・崩壊せず、一定の補修を行えば住み続けられる可能性が高い。
- 耐震等級3
- 震度6強~7
- 強度の目安 (建築基準法の何倍か):1.5倍
- 地震後の建物への影響と生活:倒壊・崩壊せず、ごく軽い補修で住み続けられる可能性が非常に高い。
耐震等級1:建築基準法で定められた最低限の備え
耐震等級1は、建築基準法で定められている最低限の耐震性能を満たすレベルです。
これは、数百年に一度発生するとされる大地震(震度6強から7程度)が起きても、建物が即座に倒壊・崩壊せず、住民が避難する時間を確保することを目的としています。
つまり、あくまで「命を守る」ための最低ラインであり、一度大きな地震を経験した後は、建物が大きく損傷し、大規模な修繕や建て替えが必要になる可能性があります。
財産である家を守り、地震後も安心して住み続けることを考えると、十分とは言えないケースがあることを理解しておく必要があります。
耐震等級2:長期優良住宅や避難所レベルの強度
耐震等級2は、等級1の1.25倍の地震力に耐えられる強度を持つと定義されています。
これは、災害時の避難場所に指定される学校や病院といった公共施設に求められる耐震性能と同じレベルです。
また、長期間にわたって良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅を認定する「長期優良住宅」では、耐震等級2以上が必須条件の一つとなっています。
公的なお墨付きがある高い信頼性を持つ水準であり、大きな地震の後でも、一定の補修を行えば住み続けられる可能性が高いレベルです。
耐震等級3:消防署レベルの最高等級|熊本地震でも倒壊ゼロ
耐震等級3は、住宅性能表示制度で定められた耐震性の中で最も高いレベルであり、等級1の1.5倍の地震力に耐える性能を持ちます。
災害時の救護活動や復興の拠点となる消防署や警察署といった、極めて高い安全性が求められる建物と同等の基準です。
その優れた性能は、2016年に発生した熊本地震でも証明されました。
この地震では、震度7の揺れが2度も観測されるという激しいものでしたが、ある調査では耐震等級3で設計された木造住宅に倒壊・全壊・半壊といった大きな被害は一棟もなかったと報告されています。
この事実は、家族の命と財産を確実に守りたいと考える方にとって、非常に心強いデータと言えるでしょう。
注意!「耐震等級3相当」と「耐震等級3」は違う?
住宅の広告やパンフレットを見ていると、「耐震等級3相当」という言葉を目にすることがあります。
しかし、これには注意が必要です。
正式な「耐震等級3」は、国が定めた第三者機関に申請し、厳密な審査を経て「住宅性能評価書」という証明書が交付されたものを指します。
一方で「耐震等級3相当」とは、ハウスメーカーなどが自社の基準や計算に基づいて、「等級3と同等の性能がある」と主張している状態です。
もちろん、高い性能を持っていることに違いはないかもしれませんが、客観的な証明があるわけではありません。
後で「こんなはずではなかった」と後悔しないためにも、その性能が正式な評価書によって裏付けられているのかどうかを確認することが非常に重要です。
なぜ重要?耐震等級を高くするメリット【安全性・資産価値・費用】

耐震等級を高くすることは、単に地震に強くなるというだけではありません。
家族の安全はもちろん、住宅の資産価値や、保険料・ローンといった費用面にも大きなメリットをもたらします。
ここでは、そのメリットを「①安全性」「②資産価値」「③費用面」の3つの観点から詳しく見ていきましょう。
メリット① 安全性:大地震後も住み続けられる安心感
耐震等級を高くする最大のメリットは、何といってもその安全性です。
特に耐震等級3の住宅は、一度の大きな本震だけでなく、その後に繰り返し発生する「余震」に対しても建物の損傷を最小限に抑えることができます。
これにより、多くの被災者が直面する避難所での不自由な生活を避け、住み慣れた我が家で生活を継続できる可能性が格段に高まります。
これは家族の身体的な安全だけでなく、精神的な負担を大きく軽減することにも繋がり、日々の暮らしの根底にある災害への不安を解消してくれます。
メリット② 資産価値:将来の売却時にも有利に
住宅性能評価書によって証明された高い耐震等級は、その住宅の客観的な「付加価値」となります。
将来、何らかの理由で家を売却することになった場合、この性能評価は買い手に対して絶大なアピールポイントになります。
中古住宅市場において、買い手は目に見えない構造の安全性を気にします。
「耐震等級3」という明確な指標があれば、安心して購入を決断しやすく、結果として売却がスムーズに進んだり、周辺の物件よりも有利な条件で取引できたりする可能性が高まります。
これは、住宅を長期的な資産として捉える上で非常に重要なポイントです。
メリット③ 費用面:地震保険の割引や住宅ローン金利の優遇
高い耐震性能を持つ住宅は、初期の建築コストはかかりますが、長期的に見ると費用面でのメリットも享受できます。
代表的なものが、地震保険料の割引制度です。
- 耐震等級1→10%
- 耐震等級2→30%
- 耐震等級3→50%
上記のように、耐震等級3を取得すると、保険料が半額になります。
これは、家計にとって大きなメリットと言えるでしょう。
さらに、一部の金融機関が提供する住宅ローン、例えば【フラット35】Sでは、耐震等級などの優れた性能を持つ住宅に対して金利の優遇措置を設けています。
初期コストの増加分を、こうした保険料の割引やローンの金利優遇によって、長期的に回収していくことも十分に可能です。
デメリットは?知っておきたい費用と間取りの注意点

多くのメリットがある一方で、耐震等級を高くすることにはデメリットや注意点も存在します。
良い面と悪い面の両方を理解した上で、総合的に判断することが大切です。
主なデメリットは「建築コストの増加」と「間取りの制約」の2つです。
耐震性を高めるためには、より強固な部材を使用したり、壁の量を増やしたり、専門家による複雑な構造計算が必要になったりします。
これらには当然追加の費用がかかり、一般的に建築コストは割高になる傾向があります。
また、地震の力に対抗するためには、建物を支える「耐力壁」をバランス良く、かつ十分な量だけ配置する必要があります。
そのため、「壁一面の大きな窓」や「柱のない広々としたリビング」といった、開放的な間取りの実現が難しくなる場合があります。
希望するデザインと、確保したい耐震性のバランスをどう取るかが、設計段階での重要な課題となります。
デザイン性と耐震等級3を両立!R-GRAPHの家づくり

「耐震性を追求すると、デザインの自由度が下がるのでは?」という懸念をお持ちの方も多いかもしれません。
しかし、高い技術力と設計力があれば、最高の安全性と理想のデザインを両立させることは可能です。
私たちR-GRAPHでは、お客様に永く安心して暮らしていただくため、すべての注文住宅で「耐震等級3」を標準仕様としています。
その上で、経験豊富な建築家と密に連携することで、お客様一人ひとりのライフスタイルやこだわりを反映した、デザイン性の高い住まいを実現しています。
例えば、猫と快適に暮らすために設計された「猫と暮らすコートハウス」では、UA値0.42W/㎡・K、C値0.29㎠/㎡という高い住宅性能と耐震等級3を確保しながら、中庭を設けることで採光とプライバシー、そして猫の安全まで考慮したデザインが評価され、「建築実例コンテスト」で2023年度優秀賞を受賞しました。
R-GRAPHは、東大阪・奈良エリアを中心に年間25棟以上の設計・施工実績を持ち、過去2年間の顧客満足度調査では90%以上のお客様から「満足」との評価をいただいています。
耐震性という安心の土台の上に、お客様だけの「とっておきの幸せ」を形にする。それが私たちの家づくりです。
検討中の家は大丈夫?耐震等級の調べ方と認定の受け方

ここまで読んで、ご自身が検討している物件や、今お住まいの家の耐震等級が気になった方もいるのではないでしょうか。
ここからは、実際に耐震等級を確認する方法と、正式な認定を受けるための手順について、具体的に解説していきます。
【新築/中古/既存】住宅の耐震等級を確認する方法
住宅の状況によって、確認方法は異なります。
以下の表を参考に、ご自身のケースに合わせて確認してみてください。
- 新築(注文住宅)
ハウスメーカーや工務店に設計段階で希望の等級を伝え、設計図書や住宅性能評価書で確認する。 - 新築(建売住宅)
不動産会社に「住宅性能評価書」の有無を確認する。 評価書がない場合は、設計図書(構造計算書など)を見せてもらい、性能を確認する。 - 中古住宅
売主や不動産会社に「住宅性能評価書」や「長期優良住宅認定通知書」がないか確認する。 書類がない場合は、建築時の設計図書を取り寄せ、専門家に確認してもらう。 - 現在住んでいる家
建築時の書類(確認済証、設計図書、住宅性能評価書など)を探す。 書類が見つからない場合は、自治体や専門機関に「耐震診断」を依頼する。
耐震等級の認定を受ける流れと費用
正式な耐震等級の認定は「住宅性能表示制度」を利用して行います。
国土交通大臣が指定した第三者評価機関に申請し、設計段階と建設段階の2回、検査を受けるのが一般的です。
- 評価機関の選定・相談
- 設計住宅性能評価の申請(設計図書の提出)
- 設計段階の検査・評価書の交付
- 建設住宅性能評価の申請
- 建設段階の現場検査(通常4回程度)
- 建設住宅性能評価書の交付
このプロセスにかかる費用は、住宅の規模や評価機関によって異なりますが、設計と建設の両方の評価を合わせて、10万円から30万円程度が目安となります。
建築コストに加えて必要な費用ですが、客観的な性能証明と将来の安心を得るための投資と考えることができます。
【専門家が解説】2025年法改正で耐震性はさらに重要に

住宅の耐震性は、近い将来さらに重要度を増すことが予想されています。
その背景にあるのが、2025年4月に施行された建築基準法の改正です。
この改正により、すべての新築住宅で「省エネ基準」への適合が義務化されました。
断熱性能を高めるなどして省エネ基準を満たすと、壁や天井の断熱材が厚くなるため、建物全体の重量が増加する傾向にあります。
建物は重くなるほど、地震の揺れによる影響を大きく受けるようになります。
そのため、これからの家づくりでは、省エネ性能と合わせて、構造計算に裏付けられた高い耐震性能を確保することが、これまで以上に不可欠となるのです。
まとめ:家族の未来を守るために、耐震等級を正しく理解して後悔のない家選びを

今回は、住宅の耐震等級について、等級1・2・3の違いからメリット・デメリット、調べ方まで詳しく解説しました。
- 耐震等級1は最低限の基準。命は守れるが、地震後に住み続けられない可能性がある。
- 耐震等級2は避難所レベル。長期優良住宅の基準でもあり、一定の安心感が得られる。
- 耐震等級3は消防署レベルの最高等級。大地震後も住み続けられる可能性が最も高い。
耐震等級の高い住宅は、初期コストがかかる一方で、地震保険料の割引や住宅ローンの金利優遇、そして何より「家族の安全」という、お金には代えがたい価値をもたらします。
耐震等級は、単なる建物のスペックではありません。
それは、大切な家族の命と財産、そして未来の安心な暮らしを守るための重要な「投資」です。
この記事で得た知識が、あなたが自信を持って後悔のない家選びをするための一助となれば幸いです。